専修人の本_2023年度
2023年度 新刊紹介

古代アメリカ文明 マヤ・アステカ・ナスカ・インカの実像
発売日 2023.12.14
共 著 井上 幸孝
発 行 講談社現代新書
価 格 税込1,320円
共 著 井上 幸孝
発 行 講談社現代新書
価 格 税込1,320円
アメリカ大陸には、メソアメリカ(メキシコと中米)とアンデス(南米)という2地域に1次文明が興った。本書はその双方を同時に扱った初の新書である。日本の世界史教育の中で軽視されてきた両文明のうち、前者についてはマヤとアステカ、後者についてはナスカとインカに焦点を当てている。
本書には、青山和夫氏(茨城大学)が代表を務めた大型プロジェクト(2014~18年度、科研費新学術領域「古代アメリカの比較文明論」)の成果が盛り込まれている。
この共同研究のメンバーであった4人の著者(マヤ=青山、アステカ=井上、ナスカ=坂井正人氏、インカ=大平秀一氏)がそれぞれの専門分野から最新の知見に基づいて分かりやすく解説し、その実像について論じている。
著者(いのうえ・ゆきたか)国際コミュニケーション学部教授。歴史学(メキシコ史)。
本書には、青山和夫氏(茨城大学)が代表を務めた大型プロジェクト(2014~18年度、科研費新学術領域「古代アメリカの比較文明論」)の成果が盛り込まれている。
この共同研究のメンバーであった4人の著者(マヤ=青山、アステカ=井上、ナスカ=坂井正人氏、インカ=大平秀一氏)がそれぞれの専門分野から最新の知見に基づいて分かりやすく解説し、その実像について論じている。
著者(いのうえ・ゆきたか)国際コミュニケーション学部教授。歴史学(メキシコ史)。

環境会計各論 生物多様性の会計、自治体の環境会計
発売日 2023.10.25
著 者 植田 敦紀
発 行 専修大学出版局
価 格 税込2,970円
著 者 植田 敦紀
発 行 専修大学出版局
価 格 税込2,970円
環境会計論については2000年代に文献が多数刊行されているが、本書ではこれまで会計対象として研究が希薄だった生物多様性の会計、及び筆者が居住している川崎市水道局の事例を取り上げ自治体の環境会計について論述している。
生物多様性問題については23年9月にTNFDより自然関連財務情報開示フレームワークが公表されたが、本書ではその根本的な問題に対して会計的立場から検討する。また自治体の環境会計については環境保全施策を効率的・効果的に推進する評価システムとしての役割を考える。
本書に続き本年度、環境会計情報のうち財務情報(オンバランス)については『環境財務会計各論』、非財務情報(オフバランス)については『サステナビリティ会計論』を刊行しているので併せてご閲読いただきたい。
著者(うえだ・あつき)商学部教授。会計学、サステナビリティ会計研究。
生物多様性問題については23年9月にTNFDより自然関連財務情報開示フレームワークが公表されたが、本書ではその根本的な問題に対して会計的立場から検討する。また自治体の環境会計については環境保全施策を効率的・効果的に推進する評価システムとしての役割を考える。
本書に続き本年度、環境会計情報のうち財務情報(オンバランス)については『環境財務会計各論』、非財務情報(オフバランス)については『サステナビリティ会計論』を刊行しているので併せてご閲読いただきたい。
著者(うえだ・あつき)商学部教授。会計学、サステナビリティ会計研究。

不作為犯論の諸相
発売日 2023.11.7
著 者 日髙 義博
発 行 成文堂
価 格 税込7,150円
著 者 日髙 義博
発 行 成文堂
価 格 税込7,150円
本書は、不真正不作為犯論の理論的核心を縦糸として、不作為犯論が他の領域においてどのような理論的広がりを持っているのかという不作為犯論の横糸の問題を浮き彫りにしたものである。
不作為犯論と過失犯論、未遂犯論、共犯論などが交錯する領域において、どのような理論的横糸を組み込むかは大きな課題である。ここでは、法解釈論、判例研究の方法論、更には法存在論等の法哲学的考察が必要である。
本書は、刑法解釈のあり方を叙述した第1部「論説」、刑事判例の動向を分析した第2部「判例研究」、不作為犯論の基礎にある法学方法論・法哲学等に関する第3部「法の基礎にあるもの」から構成されている。
これによって、不作為犯論の理論的な縦軸と横軸を示し、その体系構築の全容を解き明かしたものであるが、著者の約50年の研究の道のりを示すものでもある。
著者(ひだか・よしひろ)学校法人専修大学総長。名誉教授。刑法。
不作為犯論と過失犯論、未遂犯論、共犯論などが交錯する領域において、どのような理論的横糸を組み込むかは大きな課題である。ここでは、法解釈論、判例研究の方法論、更には法存在論等の法哲学的考察が必要である。
本書は、刑法解釈のあり方を叙述した第1部「論説」、刑事判例の動向を分析した第2部「判例研究」、不作為犯論の基礎にある法学方法論・法哲学等に関する第3部「法の基礎にあるもの」から構成されている。
これによって、不作為犯論の理論的な縦軸と横軸を示し、その体系構築の全容を解き明かしたものであるが、著者の約50年の研究の道のりを示すものでもある。
著者(ひだか・よしひろ)学校法人専修大学総長。名誉教授。刑法。
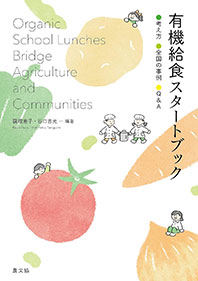
有機給食スタートブック 考え方・全国の事例・Q&A
発売日 2023.4.4
編 著 靏 理恵子
発 行 農山漁村文化協会
価 格 税込1,980円
編 著 靏 理恵子
発 行 農山漁村文化協会
価 格 税込1,980円
本書は、有機給食(オーガニック給食)に関心がある、始めたい、という読者を念頭に作られた。靍は農村社会学、谷口(秋田県立大学教授)は環境社会学を専門とする。日本有機農業学会の公開シンポジウムが契機となり、農文協の企画で誕生した一般書である。
今、有機給食への注目度が高まっている。子どもを真ん中に置いた取り組みが「地域を元気に」してきたし、しつつある。そうした有機給食の可能性、地域農業・地域社会との関係をふまえ、長い伝統を持つ所から比較的新しい所まで全国の事例を紹介した。実現に関わるハードルの越え方は、Q&Aで解説し、海外の事例やブックガイド、関連サイトも掲載した。
できるところから始めてみよう。読者の背中を知識と実践で押していけたらと願っている。
編著者(つる・りえこ)人間科学部教授。地域社会学。
今、有機給食への注目度が高まっている。子どもを真ん中に置いた取り組みが「地域を元気に」してきたし、しつつある。そうした有機給食の可能性、地域農業・地域社会との関係をふまえ、長い伝統を持つ所から比較的新しい所まで全国の事例を紹介した。実現に関わるハードルの越え方は、Q&Aで解説し、海外の事例やブックガイド、関連サイトも掲載した。
できるところから始めてみよう。読者の背中を知識と実践で押していけたらと願っている。
編著者(つる・りえこ)人間科学部教授。地域社会学。
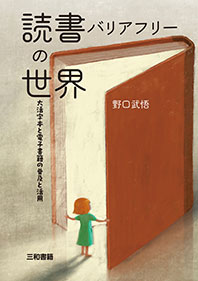
読書バリアフリーの世界: 大活字本と電子書籍の普及と活用
発売日 2023.7.20
著 者 野口 武悟
発 行 三和書籍
価 格 税込2,200円
著 者 野口 武悟
発 行 三和書籍
価 格 税込2,200円
「本の飢餓」をご存知だろうか。本が読みたくても読めない状態を指す。視覚障がい者らには点字本や音声本、大活字本といったバリアフリー図書が欠かせない。しかし、タイトル数は少なく、入手しづらい。出版物全体に占めるバリアフリー図書の割合は、先進諸国でも7%程度だ。「本の飢餓」解消に向け、「読書バリアフリー法」が2019年に制定された。
本書では、まず、前述したような動向を概観する。そのうえで、バリアフリー図書のうち普及が進む大活字本と、普及しつつある電子書籍に注目し、読書バリアフリーに果たす可能性を述べる。
7月に『ハンチバック』で芥川賞を受賞した市川沙央さんが健常者中心の読書環境の問題点を鋭く指摘し、読書バリアフリーへの関心が高まっている。読書から「誰一人取り残さない」環境づくりが急務だ。
著者(のぐち・たけのり)文学部教授。図書館情報学。
本書では、まず、前述したような動向を概観する。そのうえで、バリアフリー図書のうち普及が進む大活字本と、普及しつつある電子書籍に注目し、読書バリアフリーに果たす可能性を述べる。
7月に『ハンチバック』で芥川賞を受賞した市川沙央さんが健常者中心の読書環境の問題点を鋭く指摘し、読書バリアフリーへの関心が高まっている。読書から「誰一人取り残さない」環境づくりが急務だ。
著者(のぐち・たけのり)文学部教授。図書館情報学。

戦後政治と「首相演説」1 1945-1964
発売日 2023.9.8
著 者 藤本 一美
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,740円
著 者 藤本 一美
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,740円
岸田文雄首相は2023年1月23日、第211回通常国会の衆参本会議場において恒例の施政方針演説を行った。その際「政治とは、慎重な議論と検討を積み重ね、その上に決断し、その決断について、国会の場に集まった国民の代表が議論をし、最終的に実行に移す、そうした営みです」と述べた。だが、首相の優柔不断なさまは、その後のコロナ対策、マイナンバーカード、および閣僚の不祥事などへの一連の対応で明らかで、マスコミや国民の批判を浴びた。
本書の内容は、戦後政治の状況を踏まえて、歴代首相の施政方針演説と所信表明演説をとり上げており、国の最高責任者が何を訴え、どのような政策を行うとしたのか、その内容を批判的に論じている。
続く第2巻から第4巻では、1965年以降の首相演説を扱う予定である。
本書の内容は、戦後政治の状況を踏まえて、歴代首相の施政方針演説と所信表明演説をとり上げており、国の最高責任者が何を訴え、どのような政策を行うとしたのか、その内容を批判的に論じている。
続く第2巻から第4巻では、1965年以降の首相演説を扱う予定である。

この自由な世界と私たちの帰る場所
発売日 2023.7.11
著 者 河野 真太郎
発 行 青土社
価 格 税込1,980円
著 者 河野 真太郎
発 行 青土社
価 格 税込1,980円
本書は新自由主義とポストトゥルース時代におけるジェンダー(ポストフェミニズムにおける感情管理、トランス排除、男性性の問題)を、さまざまな映画作品を媒介に論じる前半と、レイモンド・ウィリアムズ、宮崎駿、桜庭一樹、ヴァージニア・ウルフ、村上春樹らの(文学)作品を論じながら、ポストブレグジット、ポストトランプ的な状況での「場所」論を展開する後半からなる論集である。
映画とジェンダー研究、イギリス文学とりわけウェールズ英語文学研究の成果で、多岐にわたる文章が収録されているが、とりわけウェールズ文学論を世に問えたことが大きな成果だと思っている。どこから読んでもいい本だが、個人的には、ウィリアムズの小説『ブラック・マウンテンズの人びと』と人新世について考察した第五章が白眉だと考えている。
映画とジェンダー研究、イギリス文学とりわけウェールズ英語文学研究の成果で、多岐にわたる文章が収録されているが、とりわけウェールズ文学論を世に問えたことが大きな成果だと思っている。どこから読んでもいい本だが、個人的には、ウィリアムズの小説『ブラック・マウンテンズの人びと』と人新世について考察した第五章が白眉だと考えている。
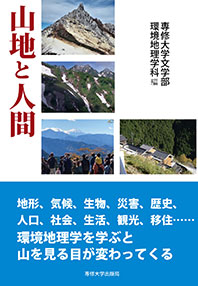
山地と人間
発売日 2023.4.17
編 集 専修大学文学部環境地理学科
発 行 専修大学出版局
価 格 税込2,640円
編 集 専修大学文学部環境地理学科
発 行 専修大学出版局
価 格 税込2,640円
日本人にとって山地は身近な存在といえる。本書は、学科の9人のスタッフが山地と人間の織りなすさまを描きだす。
山地という自然環境はどのような特色を有しているのだろうか。まずは山地の地形の成り立ち、山地特有の気候と生き物の姿、そして、山地のもたらす災害が示される。
その上で、山地を人間がどのように見て、どのように利用してきたのか。荘園図に描かれた山地、山地の占有と利用の変遷、さらには、人口の変化を明らかにする。
最後に、人口が減少する山地に、観光・レクリエーションで訪れる人々、さらには移り住もうとする人々の動向を示す。
このように、本書は地理学の立場から山地とそこにおける人間の活動を俯瞰しようとする。山地への理解を深めるとともに、地理学の見方にも触れることができよう。
山地という自然環境はどのような特色を有しているのだろうか。まずは山地の地形の成り立ち、山地特有の気候と生き物の姿、そして、山地のもたらす災害が示される。
その上で、山地を人間がどのように見て、どのように利用してきたのか。荘園図に描かれた山地、山地の占有と利用の変遷、さらには、人口の変化を明らかにする。
最後に、人口が減少する山地に、観光・レクリエーションで訪れる人々、さらには移り住もうとする人々の動向を示す。
このように、本書は地理学の立場から山地とそこにおける人間の活動を俯瞰しようとする。山地への理解を深めるとともに、地理学の見方にも触れることができよう。
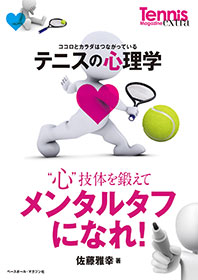
“心”技体を鍛えてメンタルタフになれ!「テニスの心理学」
発売日 2023.4.5
著 者 佐藤雅幸
発 行 ベースボール・マガジン社
価 格 税込1,980円
著 者 佐藤雅幸
発 行 ベースボール・マガジン社
価 格 税込1,980円
著者は、これまでジュニア、学生そしてトッププロまで、多くのアスリートの心理サポートをしてきました。一般的にアスリートは、細かいことにこだわらない、前向きで明るいイメージを持たれています。しかし、競技に真剣に取り組めば取り組むほど、壁に突き当たり、自分を追い込み、追い詰め、悩み、苦しんでいるのです。
本書では、著者の専門研究領域である、「スポーツ心理学」と「テニスの指導理論」を組み合わせて、アスリートが抱える心理的な問題の解決法について解説しています。これらはテニスの選手やコーチの現場での課題解決に役立つものであるとともに、一般の方々の人生におけるものの見方、考え方、生き方に応用できるものとなっています。
人生はドラマのようなものです。ときには勝ち、ときには負けて挫折します。その起伏が大きいほど人生はドラマチックになります。人生の脚本を書くのはあなた自身です。今日までのストーリーは消し去ることはできませんが、明日からのストーリーは書き直すことができるのです。ドラマの最終章をどうするか……。そのヒントが記されています。
著者(さとう・まさゆき) 経済学部教授。スポーツ研究所顧問。スポーツ心理学、テニス。
本書では、著者の専門研究領域である、「スポーツ心理学」と「テニスの指導理論」を組み合わせて、アスリートが抱える心理的な問題の解決法について解説しています。これらはテニスの選手やコーチの現場での課題解決に役立つものであるとともに、一般の方々の人生におけるものの見方、考え方、生き方に応用できるものとなっています。
人生はドラマのようなものです。ときには勝ち、ときには負けて挫折します。その起伏が大きいほど人生はドラマチックになります。人生の脚本を書くのはあなた自身です。今日までのストーリーは消し去ることはできませんが、明日からのストーリーは書き直すことができるのです。ドラマの最終章をどうするか……。そのヒントが記されています。
著者(さとう・まさゆき) 経済学部教授。スポーツ研究所顧問。スポーツ心理学、テニス。

ハマのドン 横浜カジノ阻止をめぐる闘いの記録
発売日 2023.5.17
著 者 松原文枝
発 行 集英社
価 格 税込1,056円
著 者 松原文枝
発 行 集英社
価 格 税込1,056円
横浜港湾の元締めで政財界に影響力を持つ裏の権力者"ハマのドン"こと藤木幸夫氏。御年92歳。
横浜市が進めたカジノ誘致阻止に向け、時の最高権力者と全面対決した。
決戦の場となったのは横浜市長選。藤木氏が賭けたのは、住民投票を求める署名を法定数の3倍も集めた市民の力だった。
リスク覚悟で挑んだ藤木氏の行動と市民の力が融合し、最後は政権が進めた国策をなぎ倒した。
政治を市民の手に取り戻す――。著者が制作したドキュメンタリー映画『ハマのドン』をさらに深掘りするとともに、映画が制作されるまでを記録した。
著者(まつばら・ふみえ)文学部特任教授。ジャーナリズム研究。テレビ朝日社員。
横浜市が進めたカジノ誘致阻止に向け、時の最高権力者と全面対決した。
決戦の場となったのは横浜市長選。藤木氏が賭けたのは、住民投票を求める署名を法定数の3倍も集めた市民の力だった。
リスク覚悟で挑んだ藤木氏の行動と市民の力が融合し、最後は政権が進めた国策をなぎ倒した。
政治を市民の手に取り戻す――。著者が制作したドキュメンタリー映画『ハマのドン』をさらに深掘りするとともに、映画が制作されるまでを記録した。
著者(まつばら・ふみえ)文学部特任教授。ジャーナリズム研究。テレビ朝日社員。

リスクマネジメント視点のグローバル経営―日本とアジアの関係から―
発売日 2023.4.7
編 著 上田和勇
発 行 同文舘出版
価 格 税込2,860円
編 著 上田和勇
発 行 同文舘出版
価 格 税込2,860円
本書は6人の学者と2人の実務家により執筆された。執筆者の専門領域はリスクマネジメント、保険、国際経営など実に多彩である。
本書の第1の特徴はリスクマネジメントの役割を、ステークホルダー、特に社員とその関係者のWell-beingと成長にまで拡張して、具体的に考察している点。第2の特徴はグローバル視点でのガバナンスとオペレーショナル・リスクのマネジメント問題の検討などを通じ、人的資産リスク、他者との協力関係に関するリスク、M&Aリスクなど、アジアを中心に現実に今、問題となっているリスクとそのマネジメントが考察されている点。
多くの事例とコラムにより、理論をさらに具象化して読者の関心を深めやすくなっている。
多様な文化との共生が求められる日本とアジア諸国とのグローバル経営において、これら多様な視点から分かりやすく解説する本書は学生、ビジネスマンにも推奨できる良書である。
編著者(うえだ・かずお)名誉教授。リスクマネジメント、保険、企業倫理。
本書の第1の特徴はリスクマネジメントの役割を、ステークホルダー、特に社員とその関係者のWell-beingと成長にまで拡張して、具体的に考察している点。第2の特徴はグローバル視点でのガバナンスとオペレーショナル・リスクのマネジメント問題の検討などを通じ、人的資産リスク、他者との協力関係に関するリスク、M&Aリスクなど、アジアを中心に現実に今、問題となっているリスクとそのマネジメントが考察されている点。
多くの事例とコラムにより、理論をさらに具象化して読者の関心を深めやすくなっている。
多様な文化との共生が求められる日本とアジア諸国とのグローバル経営において、これら多様な視点から分かりやすく解説する本書は学生、ビジネスマンにも推奨できる良書である。
編著者(うえだ・かずお)名誉教授。リスクマネジメント、保険、企業倫理。

事実はどこにあるのか
民主主義を運営すためのニュースの見方
発売日 2023.3.29
著 者 澤康臣
発 行 幻冬舎新書
価 格 税込1,100円
著 者 澤康臣
発 行 幻冬舎新書
価 格 税込1,100円
報道と広報を分かつのは何か。ニュースとSNSの差は何か――ジャーナリズムがなぜ必要かを考える書である。
実例を多数紹介した。東京医大の女性差別入試、富山市議たちの政務活動費不正など調査報道の裏側も、米国で倫理問題の論議となった報道も実在するエピソードの「実録」を基本とした。
本書は「民主主義の『運営側』」という生硬な表現をあえて繰り返す。私たち市民は社会のお客様ではない、主権者であり参加と自治の主人公だと訴える。そこに報道の、エンタメや生活情報を超える意味がある。
だから良い報道を渇望する市民でありたい。そして、そんな市民になろうとする学生たちの支えにしてほしい本である。
著者(さわ・やすおみ)文学部教授。新聞学、ジャーナリズム研究。
実例を多数紹介した。東京医大の女性差別入試、富山市議たちの政務活動費不正など調査報道の裏側も、米国で倫理問題の論議となった報道も実在するエピソードの「実録」を基本とした。
本書は「民主主義の『運営側』」という生硬な表現をあえて繰り返す。私たち市民は社会のお客様ではない、主権者であり参加と自治の主人公だと訴える。そこに報道の、エンタメや生活情報を超える意味がある。
だから良い報道を渇望する市民でありたい。そして、そんな市民になろうとする学生たちの支えにしてほしい本である。
著者(さわ・やすおみ)文学部教授。新聞学、ジャーナリズム研究。
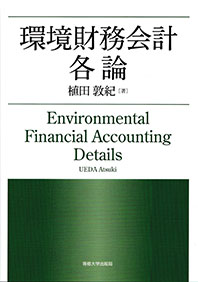
環境財務会計各論
発売日 2023.3.10
著 者 植田敦紀
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,740円
著 者 植田敦紀
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,740円
環境財務会計領域では、環境会計情報を財務会計制度の中で適正に認識することを追究する。
本領域全般については2008年拙著『環境財務会計論』において論考済みであるが、それから15年経過し、その後の社会情勢の変化に対して各論を追筆刊行した。
具体的には、11年東日本大震災に伴う福島第1原発事故による土壌汚染の会計、今後廃炉が進む原子力発電施設の廃炉の会計、更に39年ごろ太陽光パネルの大量廃棄が予測される太陽光発電施設の除去債務の会計、また温暖化対策として市場メカニズムを利用した排出量取引および各種カーボンクレジットについて論述した。
私自身の研究は、環境会計、環境財務会計、サステナビリティ会計へと進み、本年『環境会計各論』、本書、『サステナビリティ会計論』の3冊の刊行に至った。
広い視野で真に社会において必要な会計を探究していきたい。
著者(うえだ・あつき)商学部教授。会計学、サステナビリティ会計研究。
本領域全般については2008年拙著『環境財務会計論』において論考済みであるが、それから15年経過し、その後の社会情勢の変化に対して各論を追筆刊行した。
具体的には、11年東日本大震災に伴う福島第1原発事故による土壌汚染の会計、今後廃炉が進む原子力発電施設の廃炉の会計、更に39年ごろ太陽光パネルの大量廃棄が予測される太陽光発電施設の除去債務の会計、また温暖化対策として市場メカニズムを利用した排出量取引および各種カーボンクレジットについて論述した。
私自身の研究は、環境会計、環境財務会計、サステナビリティ会計へと進み、本年『環境会計各論』、本書、『サステナビリティ会計論』の3冊の刊行に至った。
広い視野で真に社会において必要な会計を探究していきたい。
著者(うえだ・あつき)商学部教授。会計学、サステナビリティ会計研究。

異文化コミュニケーション―自文化と異文化の理解をめざして
発売日 2023.1.20
著 者 上村 妙子
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,080円
著 者 上村 妙子
発 行 専修大学出版局
価 格 税込3,080円
本書は4部構成となっており、第1部では「文化」とは何かを探り、その定義、特徴、種類を扱っています。
さらに、「異文化」間における相違を見える文化と見えない文化という二つの側面から説明しています。
第2部では、言語による「コミュニケーション」に焦点を当て、主に日本語と英語を語彙、文、文章のレベルに分けて比較しています。
第3部では、非言語による「コミュニケーション」を取り上げ、日本と欧米のコミュニケーション・スタイルの違いを説明しています。
最後に、第4部では、第2部と第3部での議論を踏まえ、言語と非言語がどのように一体となってメッセージを伝え、コミュニケーションを成立させているのかを探っています。
著者(かみむら・たえこ)文学部教授。応用言語学、英語教育。
さらに、「異文化」間における相違を見える文化と見えない文化という二つの側面から説明しています。
第2部では、言語による「コミュニケーション」に焦点を当て、主に日本語と英語を語彙、文、文章のレベルに分けて比較しています。
第3部では、非言語による「コミュニケーション」を取り上げ、日本と欧米のコミュニケーション・スタイルの違いを説明しています。
最後に、第4部では、第2部と第3部での議論を踏まえ、言語と非言語がどのように一体となってメッセージを伝え、コミュニケーションを成立させているのかを探っています。
著者(かみむら・たえこ)文学部教授。応用言語学、英語教育。