2021.01.27 Wed
ONLINETOPICS
「学長伝書鳩」No.12
~専大生ならSDGsの理解は必須!!~
「SDGsチャレンジプログラム2020」表彰式をハイブリッドで開催!
2021年1月23日(土)、第1回となる「専修大学SDGsチャレンジプログラム2020」の表彰式が生田キャンパス3号館「蒼翼の間」で開催されました。コロナ禍にある昨年7月下旬のプレ・エントリーから始まって半年間、ほぼ全ての手続をオンラインで実行するという制約を乗り越えて、ここまでやりきったことに対し、このプログラムに関与した学生、審査員、キャリアデザインセンターそして事務局のすべての皆さまに敬意と感謝の気持ちを伝えたいと思います。
2021年1月23日(土)、第1回となる「専修大学SDGsチャレンジプログラム2020」の表彰式が生田キャンパス3号館「蒼翼の間」で開催されました。コロナ禍にある昨年7月下旬のプレ・エントリーから始まって半年間、ほぼ全ての手続をオンラインで実行するという制約を乗り越えて、ここまでやりきったことに対し、このプログラムに関与した学生、審査員、キャリアデザインセンターそして事務局のすべての皆さまに敬意と感謝の気持ちを伝えたいと思います。
専修大学でのSDGs事始め
持続可能性という必要条件を満たしたうえで、世界が2030年を目途に解決しなければならない諸課題を17の目標(169の具体目標)の形で可視化し、その目標達成のための行動を求めるというSDGsの理念は、「社会知性の開発」をめざす専修大学の21世紀ビジョンとも親和性の高いものです。
持続可能性という必要条件を満たしたうえで、世界が2030年を目途に解決しなければならない諸課題を17の目標(169の具体目標)の形で可視化し、その目標達成のための行動を求めるというSDGsの理念は、「社会知性の開発」をめざす専修大学の21世紀ビジョンとも親和性の高いものです。
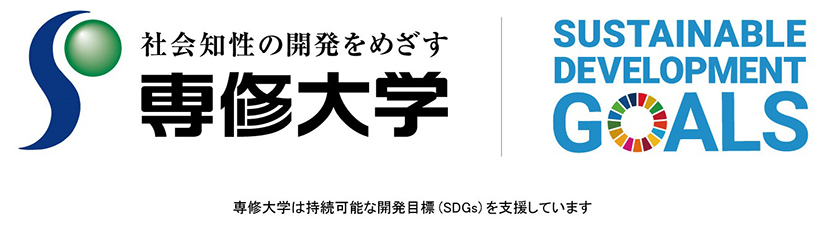
※専修大学のSDGsへの取り組みの詳細は、上の画像をクリックしてください。
本学でのSDGsの取り組みは、以上のことをいち早く認識していた本学教員による研究や教育のなかで先行的に始まりました。私がSDGsのことを直接知ることになったのは、本学経済学部の遠山浩教授がSDGsを企業に普及させるための実行資金獲得をめざして外部コンペにチャレンジしたことがきっかけでした。しかも、SDGsに関連している研究や教育の実態を把握するため、2019年後期に全学の教員を対象にしてアンケート調査を行ったところ、非常に多くの取り組みが既に存在していることもわかったのです。当然、それらの先生方の教えを受けて、SDGsに強い関心を抱いているはずの学生の存在を「見える化」する必要も感じるに至りました。そこで、2020年は「社会知性の開発」の一環としてSDGsへの取り組みを本格化させる年にしようと思ったのですが、年明けから新型コロナウイルス感染症が、日本でも徐々に広がりつつありました。
「SDGsチャレンジプログラム2020」開催に向けて突き動かしたもの
コロナ禍の影響は、本学にとっても想像以上に大きく、多方面で学生の皆さんには、制限がかかった学生生活を強いることとなりました。本学学生が日ごろの学修の成果を競う場として、毎年度学内外で開催されてきた各種のプログラムやコンペも「本年度中止」の情報が次々に発表されました。そうした中で、学生のSDGsへの関心を促す本プログラムの目的に加えて、コロナ禍の中にあっても本学学生の学修成果の発表の場を設けたいという思いを込めて「専修大学SDGsチャレンジプログラム」を企画したのです。
コロナ禍の影響は、本学にとっても想像以上に大きく、多方面で学生の皆さんには、制限がかかった学生生活を強いることとなりました。本学学生が日ごろの学修の成果を競う場として、毎年度学内外で開催されてきた各種のプログラムやコンペも「本年度中止」の情報が次々に発表されました。そうした中で、学生のSDGsへの関心を促す本プログラムの目的に加えて、コロナ禍の中にあっても本学学生の学修成果の発表の場を設けたいという思いを込めて「専修大学SDGsチャレンジプログラム」を企画したのです。
「専修大学SDGsチャレンジプログラム」の基本コンセプト
本プログラムのデザインは、学長室に事務局を置いたうえで、この分野に知見のある渡辺達朗商学部長にお願いすることとしました。その結果、「コロナ禍での本学学生によるSDGsに係るアイデアとアクションについて、学外からの評価にも耐えうる充実した審査体制◆で評価し、学生の持続的活動を促し、優れたアイデアの実現に対して大学がサポートする★」というコンセプトのもと、本プログラムの基本プランができあがりました。本プログラムの実施を学内で公表した当初、急遽の船出となったこの試みに、どれほどの応募があるのか、少し不安ではありましたが、アイデアコンテストとアクションコンテストに合計23のエントリーがあると知ったときは、とても嬉しかったことを思い起こします。
◆「専修大学SDGsチャレンジプログラム」審査員(学内・学外五十音順・敬称略)
★「専修大学SDGsチャレンジプログラム」サポート体制
本プログラムのデザインは、学長室に事務局を置いたうえで、この分野に知見のある渡辺達朗商学部長にお願いすることとしました。その結果、「コロナ禍での本学学生によるSDGsに係るアイデアとアクションについて、学外からの評価にも耐えうる充実した審査体制◆で評価し、学生の持続的活動を促し、優れたアイデアの実現に対して大学がサポートする★」というコンセプトのもと、本プログラムの基本プランができあがりました。本プログラムの実施を学内で公表した当初、急遽の船出となったこの試みに、どれほどの応募があるのか、少し不安ではありましたが、アイデアコンテストとアクションコンテストに合計23のエントリーがあると知ったときは、とても嬉しかったことを思い起こします。
◆「専修大学SDGsチャレンジプログラム」審査員(学内・学外五十音順・敬称略)
廣瀬 玲子 (本学文学部教授・図書館長)【審査員長】
田中 隆之 (本学経済学部教授・キャリアデザインセンター長)
相原 剛史 (川崎市多摩区役所まちづくり推進部企画課)
腰塚 安菜 (株式会社 博報堂)
ファン・ハイ・リン(ベトナム国家大学 ハノイ人文社会科学大学 東洋学部准教授・科学評議会会長)
堀 雅美 (公益財団法人東京都環境公社)
堀 雅美 (公益財団法人東京都環境公社)
★「専修大学SDGsチャレンジプログラム」サポート体制
■キャリアデザインセンターによるSDGs優秀アイデア実現化サポート
■本プログラム入賞者のキャリア形成支援課主催「トップアップセミナー2020」への参加招待
学長賞の紹介
本プログラムの入賞チームのうち、アイデアコンテストとアクションコンテストで学長賞を受賞した2チームについて以下で紹介させていただきます。
今回のコンテストの詳細は、こちらもご覧ください。
●アイデアコンテスト学長賞
●アクションコンテスト学長賞
本プログラムの入賞チームのうち、アイデアコンテストとアクションコンテストで学長賞を受賞した2チームについて以下で紹介させていただきます。
今回のコンテストの詳細は、こちらもご覧ください。
●アイデアコンテスト学長賞
テーマ:「Share Study Project」
チーム名:商学部 奥瀬喜之ゼミナール
内容:大学教科書のリサイクルシステムを構築し、経済的に困窮する学生が安価で教科書を購入できるようにすると同時に、回収した教科書を販売して得た利益を発展途上国の教育支援や学校建設のために充てる資金として寄付する。
SDGs:目標04(質の高い教育をみんなに)・目標10(人や国の不平等をなくそう)・目標12(つくる責任 つかう責任)・目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)
●アクションコンテスト学長賞
テーマ:「いろ色!~自然たんけん隊~」
チーム名:ネットワーク情報学部 杉田プロジェクト2020
内容:生田緑地でさまざまな「色」をさがすアプリを開発した。色に対応するかわいいキャラクターが作成され、親子で楽しみながら自然に親しむことができる。
SDGs:目標11(住み続けられるまちづくりを)・目標15(陸の豊かさを守ろう)・目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)
アフターコロナ時代のSDGs
アフターコロナ時代のSDGsは、ウィズコロナ時代の経験を生かして、ますます注目されることになるでしょう。今後、このプログラムに参加したすべての皆さんがSDGsに関わる活動のインフルエンサーとしての役割も担っていただければと思います。また「社会知性の開発」をめざす専修大学の学生であれば、SDGsの理解は必須であり、具体的な行動につなげてほしいと思います。そのために「専修大学SDGsチャレンジプログラム」がお役に立てば幸いです。次回も多くのエントリーを期待しております。
アフターコロナ時代のSDGsは、ウィズコロナ時代の経験を生かして、ますます注目されることになるでしょう。今後、このプログラムに参加したすべての皆さんがSDGsに関わる活動のインフルエンサーとしての役割も担っていただければと思います。また「社会知性の開発」をめざす専修大学の学生であれば、SDGsの理解は必須であり、具体的な行動につなげてほしいと思います。そのために「専修大学SDGsチャレンジプログラム」がお役に立てば幸いです。次回も多くのエントリーを期待しております。
