2019.06.10 Mon
CALL教室・外国語教育研究室TOPICS
外国語のススメ【第93回】世界の言語・言語の世界
法学部准教授 八島 純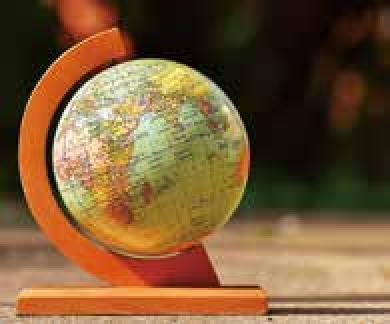
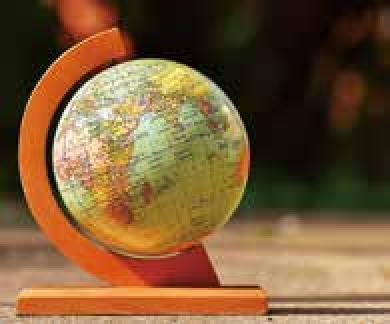
今さら説明不要だろうが、英語で"He can speak English.”は平叙文、"Can he speak English?”は疑問文である。英語の平叙文と疑問文を比較すると、主語と助動詞の順序が入れ替わっていることがわかる。日本語の場合、平叙文と疑問文の区別は語順ではなく助詞の有無によって示される。たとえば、「彼は英語を話せます」という平叙文の文末に助詞の「か」を付け加えれば「彼は英語を話せますか」という疑問文になる。
英語を学び始めた頃、「英語の疑問文の作り方ってずいぶん変だな」と思った記憶がある。ここでいう「変」というのが「(世界の言語の中では)一般的でない」という意味ならば、その時の直感は正しいのかもしれない。
The World Atlas of Language Structures (WALS: https://wals.info/) というウェブサイトでは、世界諸言語の特徴を比較することができる。たとえば、平叙文と(Yes-No型)疑問文を語順によって区別する言語を調べてみると、登録されている955言語の中でたった13言語(わずか1%強)しか該当しないことがわかる。これに対して、日本語のように助詞的な要素を使って平叙文と疑問文の区別をする言語は60%以上にものぼる。
WALSではこの他にも様々な言語の特徴について調べることができる。たとえば、英語では動詞は主語の後、目的語の前に来るので「主語―動詞―目的語」が基本語順であるが、日本語は「主語―目的語―動詞」が基本語順である。時折、「日本人の話は前置きが長くて最後まで聞かないと結論がわからない。それは、日本語が述語(動詞)を文の最後に置く言語であることが関係している」という俗説を耳にするが、WALSで世界の諸言語の基本語順(主語と目的語と動詞の相対的な順序)を調べてみると、最も多いパターンは日本語と同じ「主語―目的語―動詞」の順序であることがわかる(1,377言語中565言語)。英語のように「主語―動詞―目的語」を基本語順とする言語は二番目に多く見られるパターン(1,377言語中488言語)で、最も珍しいのは「目的語―主語―動詞」を基本語順とする言語である(1,377言語中4言語)。
世界には約7,000もの言語が存在すると言われており(興味がある人はEthnologueのウェブサイト: https://www.ethnologue.com/を参照されたい)、今後さらに多くの言語を調べたら、また新たな事実が明らかになるのかもしれない。
WALSではこの他にも様々な言語の特徴について調べることができる。たとえば、英語では動詞は主語の後、目的語の前に来るので「主語―動詞―目的語」が基本語順であるが、日本語は「主語―目的語―動詞」が基本語順である。時折、「日本人の話は前置きが長くて最後まで聞かないと結論がわからない。それは、日本語が述語(動詞)を文の最後に置く言語であることが関係している」という俗説を耳にするが、WALSで世界の諸言語の基本語順(主語と目的語と動詞の相対的な順序)を調べてみると、最も多いパターンは日本語と同じ「主語―目的語―動詞」の順序であることがわかる(1,377言語中565言語)。英語のように「主語―動詞―目的語」を基本語順とする言語は二番目に多く見られるパターン(1,377言語中488言語)で、最も珍しいのは「目的語―主語―動詞」を基本語順とする言語である(1,377言語中4言語)。
世界には約7,000もの言語が存在すると言われており(興味がある人はEthnologueのウェブサイト: https://www.ethnologue.com/を参照されたい)、今後さらに多くの言語を調べたら、また新たな事実が明らかになるのかもしれない。