2024.11.19 Tue
人間文化学科トピックス一覧
【人間文化学科】大川小学校の裏山で学ぶ震災~語り部活動を体験
令和6年11月1日(金)、人間文化学科1年生を対象とした授業「フレッシュマンセミナー」の一環として、震災語り部活動を体験しました。
当日は震災遺構である旧大川小学校に赴き、「大川伝承の会」の共同代表を務める鈴木典行さんから震災当時に大川小学校で起こった出来事についてお話いただき、その後児童たちが避難しようとした山道を実際に歩きました。また鈴木さん自身がなぜ語り部活動を行っているのかについてもお話いただきました。
大川小学校で起きた出来事については、生存した児童からの証言をもとに話しています。
震災発生後、児童と先生たちは、学校の校庭に避難しました。避難した児童たちの中には、「裏山へ逃げよう」と声をかけた子もいましたが、当時のハザードマップの想定では津波が来ない場所になっていたこと、大川小学校が避難場所になっていたことから、大川小学校の先生たちは川沿いの三角地帯へ移動する選択をしました。その結果、多くの児童と先生たちが津波の犠牲となりました。
語り部活動を体験した当日は、児童たちがたどり着けなかった裏山へ案内していただきました。
鈴木さんは、当時大川小学校に通っていた娘さんを亡くしました。
津波到達地点を越えた見晴台に立ち、小学校を眺める皆を前にして、鈴木さんは自分にとっていつまでも振り返ることの苦しいこの場所で語り部活動を続ける意義を話してくれました。
この経験を次の世代に必ず伝えていかなければならないというこの石巻地域の課題を、学科の1年生が実感できた非常に貴重な経験になりました。
当日は震災遺構である旧大川小学校に赴き、「大川伝承の会」の共同代表を務める鈴木典行さんから震災当時に大川小学校で起こった出来事についてお話いただき、その後児童たちが避難しようとした山道を実際に歩きました。また鈴木さん自身がなぜ語り部活動を行っているのかについてもお話いただきました。
大川小学校で起きた出来事については、生存した児童からの証言をもとに話しています。
震災発生後、児童と先生たちは、学校の校庭に避難しました。避難した児童たちの中には、「裏山へ逃げよう」と声をかけた子もいましたが、当時のハザードマップの想定では津波が来ない場所になっていたこと、大川小学校が避難場所になっていたことから、大川小学校の先生たちは川沿いの三角地帯へ移動する選択をしました。その結果、多くの児童と先生たちが津波の犠牲となりました。
語り部活動を体験した当日は、児童たちがたどり着けなかった裏山へ案内していただきました。
鈴木さんは、当時大川小学校に通っていた娘さんを亡くしました。
津波到達地点を越えた見晴台に立ち、小学校を眺める皆を前にして、鈴木さんは自分にとっていつまでも振り返ることの苦しいこの場所で語り部活動を続ける意義を話してくれました。
この経験を次の世代に必ず伝えていかなければならないというこの石巻地域の課題を、学科の1年生が実感できた非常に貴重な経験になりました。
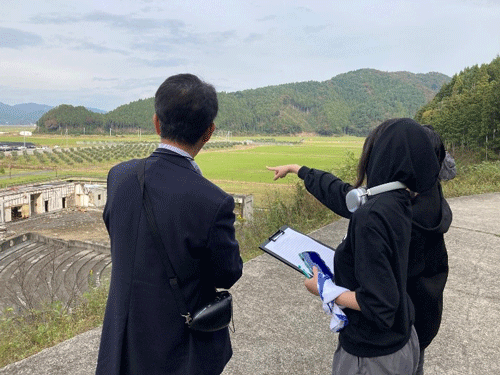
▲裏山から望む旧大川小学校
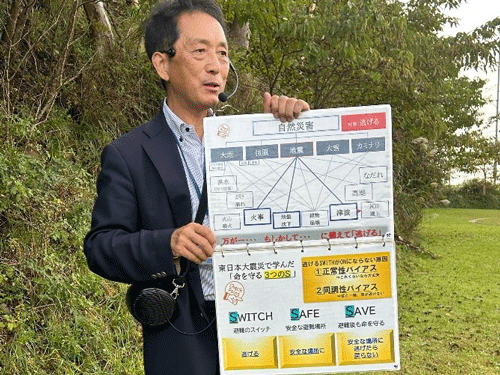
▲訓練の重要性を説く鈴木典行さん
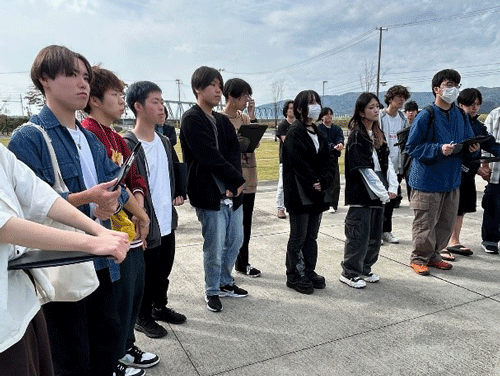
▲被害の大きさに聞き入る学生たち
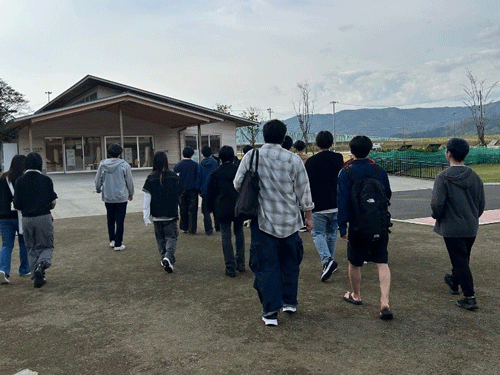
▲当時の避難経路を実際にたどる

▲児童は「津波到達点」の上でも活動していました

▲裏山へも足を運びました

▲鈴木さんに当時の様子を質問
【学生の感想】
□谷口 璃珠さん(人間文化学科1年次、第一学院高等学校出身)
鈴木さん自身、震災で辛い思いをしたにも関わらず後世に伝えるため、ご自身の辛い経験を語っていただいたことに感銘しました。インターネットや本で情報を得る機会はありますが、体験した方から直接お話いただく機会はありませんので貴重な経験になりました。私自身、震災当時は5歳だったということもあり、当時の記憶は残っているものの、地震と津波のことについては覚えていません。小さいながら大変だったことだけは覚えています。鈴木さんのお話を聞き、この場所で多くの方々が亡くなったこと、そこから復興に向け多くの方々が震災と向き合ってきたこと、沢山の学びがありました。
□佐々木 碧唯さん(人間文化学科1年次、岩手県立一関第二高等学校出身)
大川小学校の語り部活動を見学して、改めて震災の脅威と日頃から備えることの大切さを実感した。震災当時、私は岩手県釜石市に住んでいたため、津波の恐怖や惨状を覚えています。今回の見学で、そのことを振り返ることになりました。大川小学校には近くに避難できる高台がありましたが、避難せずに待機してしまったことから、多くの犠牲者を出てしまいました。悲劇を繰り返さないために、日頃から災害が起きた時の避難ルートや防災バッグ、そして学校等で行われる避難訓練にしっかり取り組み、備えたいと思います。また、語り継いでいくことの重要性を学びましたので、私自身ができる活動については積極的に取り組んでいきたいです。
□谷口 璃珠さん(人間文化学科1年次、第一学院高等学校出身)
鈴木さん自身、震災で辛い思いをしたにも関わらず後世に伝えるため、ご自身の辛い経験を語っていただいたことに感銘しました。インターネットや本で情報を得る機会はありますが、体験した方から直接お話いただく機会はありませんので貴重な経験になりました。私自身、震災当時は5歳だったということもあり、当時の記憶は残っているものの、地震と津波のことについては覚えていません。小さいながら大変だったことだけは覚えています。鈴木さんのお話を聞き、この場所で多くの方々が亡くなったこと、そこから復興に向け多くの方々が震災と向き合ってきたこと、沢山の学びがありました。
□佐々木 碧唯さん(人間文化学科1年次、岩手県立一関第二高等学校出身)
大川小学校の語り部活動を見学して、改めて震災の脅威と日頃から備えることの大切さを実感した。震災当時、私は岩手県釜石市に住んでいたため、津波の恐怖や惨状を覚えています。今回の見学で、そのことを振り返ることになりました。大川小学校には近くに避難できる高台がありましたが、避難せずに待機してしまったことから、多くの犠牲者を出てしまいました。悲劇を繰り返さないために、日頃から災害が起きた時の避難ルートや防災バッグ、そして学校等で行われる避難訓練にしっかり取り組み、備えたいと思います。また、語り継いでいくことの重要性を学びましたので、私自身ができる活動については積極的に取り組んでいきたいです。
- 人間文化学科の学生や教員の日常生活を紹介した学科公式Instagramもぜひご覧ください!