2020.07.06 Mon
人間学部TOPICS
【人間文化学科】中国語中級Ⅰをオンライン授業で実施
6月19日(金)、人間学部人間文化学科の輪田直子教授が担当する「中国語中級Ⅰ」のオンライン授業を取材しました。この授業は、初級の中国語学習を終えた学生を対象に、中国語の「読み、書き、聴き、話す」能力を総合的に高めることを目指しています。
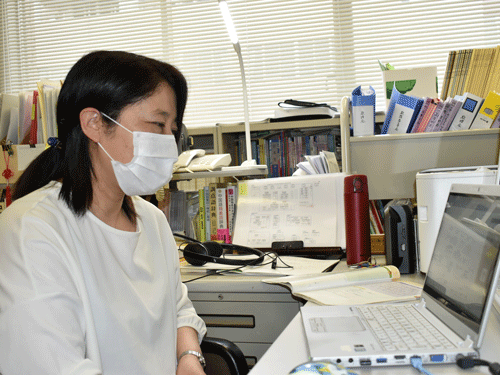 ▲オンライン授業をする輪田先生
▲オンライン授業をする輪田先生 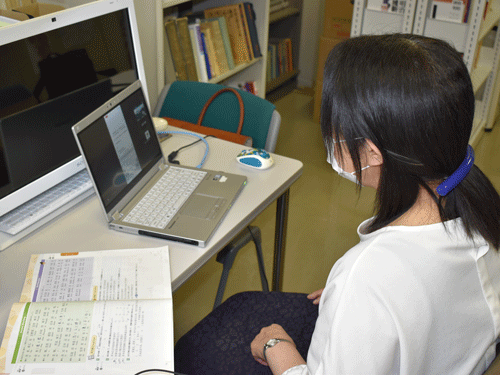 ▲テキストも使って授業をしています
▲テキストも使って授業をしています この日は、まず事前に課されていた、週末の予定を中国語で作文したものを音読し、発音や文法の確認を行いました。
次に、テキストに沿って中国語の音声を流し、学生が発声。それを聞いた輪田先生が発声のコツについて、「口を大きく開ける、息をもっと出す」といった具体的な指導を行いました。その後、発声した中国語を日本語に訳したり、日本語の文章を中国語に作文し、Zoomを使って先生や他の学生と共有したりしました。この、リスニング、リーディング、ライティングを繰り返すことによって、着実に中国語の力がついていきます。
受講している学生は、わからないことがあると、すぐに先生に質問し、その場で解決。ただ単位を取れればいいという姿勢ではなく、中国語をしっかりと身につけようとしている姿勢を見ることができました。
次に、テキストに沿って中国語の音声を流し、学生が発声。それを聞いた輪田先生が発声のコツについて、「口を大きく開ける、息をもっと出す」といった具体的な指導を行いました。その後、発声した中国語を日本語に訳したり、日本語の文章を中国語に作文し、Zoomを使って先生や他の学生と共有したりしました。この、リスニング、リーディング、ライティングを繰り返すことによって、着実に中国語の力がついていきます。
受講している学生は、わからないことがあると、すぐに先生に質問し、その場で解決。ただ単位を取れればいいという姿勢ではなく、中国語をしっかりと身につけようとしている姿勢を見ることができました。
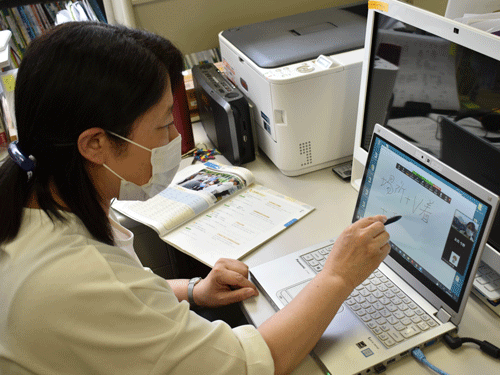 ▲オンライン授業でも板書できます
▲オンライン授業でも板書できます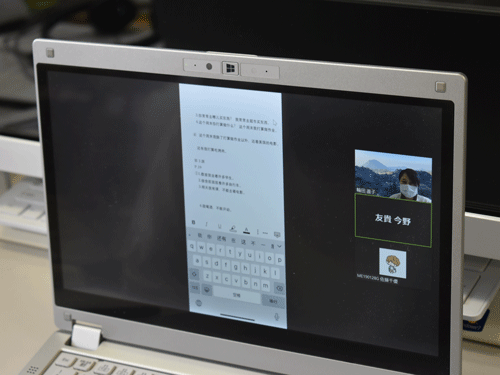 ▲学生が作文したものを先生と共有
▲学生が作文したものを先生と共有【受講した学生の声】
■今野 友貴さん(人間学部人間文化学科2年次・第一学院高校出身)
中国語の授業は、コミュニケーションを図りながら行うので、顔を合わせて学びたいという気持ちもありますが、オンラインでも問題なく学習できています。また、オンライン授業は、大学への移動時間を気にせずに学べるので、かなり便利になったと感じています。
中国語の勉強を始めたきっかけは、中国への交換留学制度があることを知ったからです。交換留学前に語学力を上げるため、全日本中国語スピーチコンテスト(東北大会)にも出場しました。スピーチコンテストの参加者を対象に中国への招待旅行があったので、そこにも参加し、貴重な経験をすることができました。8月には、サマープログラムで中国の東北電力大学に10日間ほど行く予定でしたが、コロナウイルスの影響で中止になってしまいました。その代わり、7月24日(金)に中国の東北電力大学外国語学部日本語学科の学生と、Zoomでの交流授業を実施することになっています。今から、交流授業が楽しみです!
■今野 友貴さん(人間学部人間文化学科2年次・第一学院高校出身)
中国語の授業は、コミュニケーションを図りながら行うので、顔を合わせて学びたいという気持ちもありますが、オンラインでも問題なく学習できています。また、オンライン授業は、大学への移動時間を気にせずに学べるので、かなり便利になったと感じています。
中国語の勉強を始めたきっかけは、中国への交換留学制度があることを知ったからです。交換留学前に語学力を上げるため、全日本中国語スピーチコンテスト(東北大会)にも出場しました。スピーチコンテストの参加者を対象に中国への招待旅行があったので、そこにも参加し、貴重な経験をすることができました。8月には、サマープログラムで中国の東北電力大学に10日間ほど行く予定でしたが、コロナウイルスの影響で中止になってしまいました。その代わり、7月24日(金)に中国の東北電力大学外国語学部日本語学科の学生と、Zoomでの交流授業を実施することになっています。今から、交流授業が楽しみです!