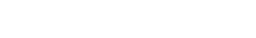- 専修大学大学院での学び >
- 修了生のメッセージ >
- 古畑 扇 さん
知識をアップデートし
⾃ら答えを⾒いだす研究の醍醐味に気付いた

商学研究科商学専攻修士課程修了(商学研究科商学専攻博⼠後期課程在籍中)
古畑 扇
幼児向け英語教材を販売する企業で販売促進業務を担いながら、専修⼤学院へ進学し、修⼠課程を修了。現在、専修⼤学⼤学院博⼠後期課程2年次在籍中。
——企業で働きながら、⼤学・⼤学院で学ぼうと思ったきっかけを教えてください。
現在勤務している会社では、乳幼児を持つ⺟親向けに英語教材の販売を⾏っています。職場では営業職のサポートを担っており、営業コミュニケーションの⼿法や顧客との成約確率などの傾向を学術⾯から捉え直し、現場に還元したいと思ったのが、専修⼤学進学のきっかけでした。当時は販促イベントでの経験や営業ノウハウが社内で共有されておらず、これらをもっと体系化したら効率よく仕事ができるのではないかと考えたのです。そこで、商学や経済学を広く学べて仕事と両⽴できる同⼤学院の⾨を叩きました。現在は博⼠課程に在籍しています。ゆくゆくは社内向けの研修などを通して、学んだ内容を社員に伝えていきたいと思っています。
——具体的な研究内容についてお聞かせください。
修⼠課程では「⺟親の乳幼児向け英語教材への知覚リスクが購買意図に及ぼす影響」と題した研究に従事。近年の調査で、8割の⺟親が「乳幼児のうちから⼦どもに英語を学ばせたいと思っている」というデータがある⼀⽅で、実際の⾏動に移せているのは、その半数以下であるというデータもありました。私は、こうした⽭盾はなぜ起こるのだろうと疑問を抱き、アンケート調査や数量的な分析を進めていきました。その結果として⺟親が購買時に感じる経済的、機能的、社会的、⾝体的、時間的な5つの知覚リスクが要因であると判明。中でも教材の購買や使⽤にかかる時間的なリスクや、ママ友や祖⽗⺟など「他者からどう⾒られるか」という社会的リスクの影響が⾊濃く反映されているという結論に⾄りました。
——⼤学院の学びから、どのような収穫を得たのでしょうか。
「研究とは、⾃分で答えを⾒つけるものである」と気づけたことです。研究を始めた当初は、先⾏研究の中に職場の課題を解決できそうな研究が沢⼭あると思っていましたし、その研究だけをまとめていけば課題は解決していくと考えていました。しかし、すぐに先⾏研究だけでは解決できないことに気が付き⾏き詰まってしまいました。このことを指導教授に相談すると、「それはただ課題について勉強しているだけであり、研究ではない。研究とは、すでに存在する解決策を探し出すことではなく、新たに⾃分の答えをつくり、⾒いだすことだ」というお⾔葉をいただきました。それ以来、「主体的に⾃分なりの答えの出し⽅を常に考え、深い考察に基づいた研究スタイルを⼼掛けよう」という意識を持つことができました。
——学部で終わらず、⼤学院まで進学されたモチベーションはどこにあったのでしょうか。
社会⼈になり、学⽣の時とは違うものの⾒⽅ができているので、⾯⽩いものを探す宝探しのような感覚で、学びを楽しめてきたことがモチベーションにつながっています。
実際に、これらが仕事に役⽴つだけでなく、持っていた知識をアップデートできたり、新しい考え⽅を増やすきっかけにもなったりしました。
そんな中で、徐々に研究を深め、成果も残したいという気持ちや、学んだ以上はそれを⽣かせる機会をつくりたいといった気持ちも⽣まれ、さらなるモチベーションアップにつながりました。
——お仕事と⼤学院との両⽴で困難を感じた経験がありますか。
仕事をしている時と研究をしている時の意識の持ち⽅に困難を感じました。
会社であれば業務内容がある程度明確に決まっているため、進み具合も分かりやすいのですが、研究だと、読んだ論⽂の意味がよく分からなかったり、最終的に⾃分の研究に使えそうか判断できなかったりと、時間を無駄にしているという焦りを感じることが度々ありました。もちろん、そうした経験の積み重ねが研究に⽣きてくるというのは判っているのですが、なかなかそのように考えることができませんでした。
このような時は、実務と研究が結び付くように研究内容を整理するなど、少しでも前に進めている実感が湧くように⼯夫をしています。